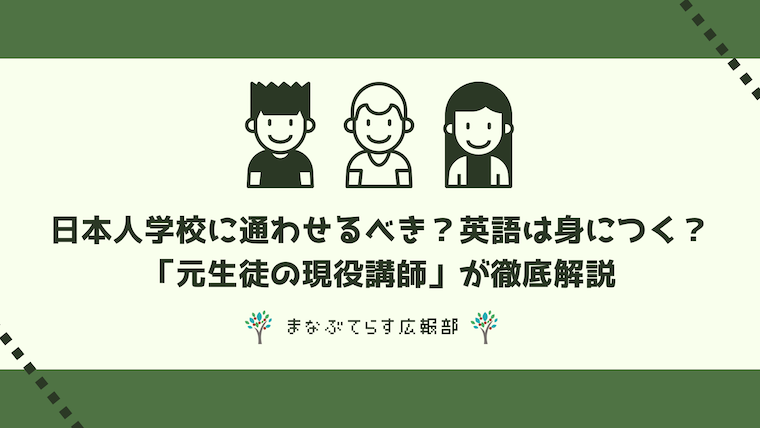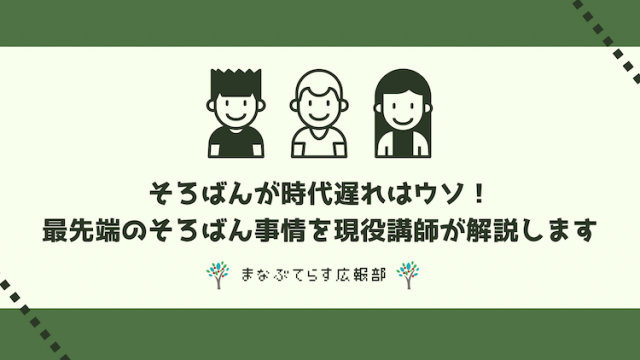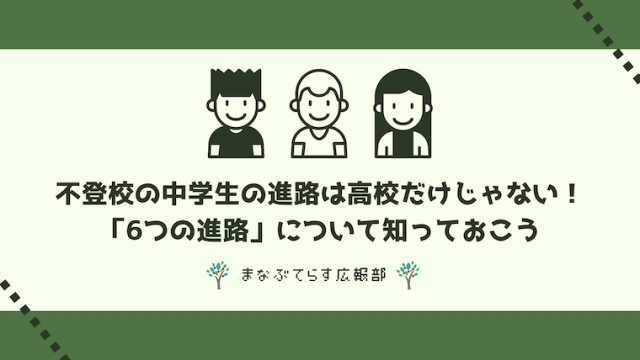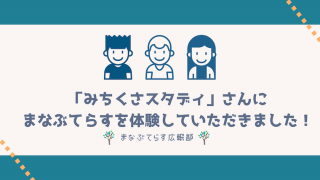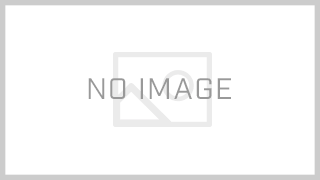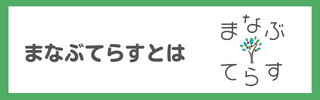子どもを持つ海外在住者にとって、「日本人学校に通わせるべきか」は非常に大きなテーマです。
現地の学校やインターナショナルスクールに通わせれば、英語などその土地の言語を習得でき、子どもの将来は無限の可能性を持ちます。
一方で、未成熟な子どもを、文化も言語も異なる環境に飛び込ませることは、極めて大きな負担となることも事実。
子どものことを考えると「どうするのが最善なのかがわからない」と悩んでしまうのも無理はありません。
そこでこの記事では、「日本人学校に通わせるべきなのか」という点について、「日本人学校の元生徒で現役のオンライン家庭教師」である筆者が、徹底的に解説していきます。
英語力が身につくのか、通ったことに後悔していないかなど、正直にお話をしていきます。
「日本人学校or現地校」どちらを選ぶべき?元生徒の経験談
日本人学校は、世界中に多くの数存在します。国の数だけ日本人学校がある、は少し言い過ぎですが、色々な場所で日本の教育を受けられるようにしてくれているので、海外在住者からすれば助かりますよね。
筆者が日本人学校に通っていた当時は、「これが普通のこと」と思いながら毎日学校に通っていましたが、日本に帰国してから振り返ると、「本当に特別な経験をした」という感想が出てきます。
また、母親に当時の話を聞いてみると、下記のように当時の心境を吐露してくれます。
- 現地校(インターナショナルスクール)と迷いに迷った
- 自分(母親)が日本語しか話せないから通わせるのが不安だった
- まだ小さい子どもを現地の学校に預けるのが不安だった
日本人学校に通うパターンはいくつかあると思いますが、筆者は父親の仕事の関係でアジア圏へと転勤をした「日本で育って海外へと生活を移した」パターンです。
「海外で育ってそのまま生活を継続している」パターンとは大きく異なりますが、やはり親目線になると、海外という慣れない場所での生活の中で、日本語しか話せない親と子が、いきなり現地校に飛び込むのは「無謀」に映ってもおかしくありませんよね。
結論:将来ビジョン、子どもの適正など、総合的に判断しよう
そこでまず、わかりやすく結論からですが、言うまでもなく正解はありません。
あらゆることを総合的に考慮した上で、子どもにとって最適な決断を下すことが求められます。具体的には、将来ビジョンや子どもの適正、さらには経済面もあるでしょう。
そういったことをトータルで判断した上で決断することが求められます。
なかなか難しい決断かもしれませんが、日本にいても「公立or私立」「一般校or一貫校」のような選択を迫られるので、「親として最良の決断」を下すという点では、日本にいても、海外にいても、それは変わりません。
現地の日本人学校に通ったことは今でも良い思い出
参考までに、実際に現地の日本人学校に通っていた筆者が、どのようなことを感じながら通っていたのかを振り返ってみます。
と言ったはいいものの、小学生の低学年の時に通っていたので、「ほとんど覚えていない」というのが正直なところです…(苦笑)
ですが、少なくとも悪い思い出ではありませんし、「特別な経験をした」という点では、日本に住んでいたら絶対に経験できないことだったので、ある種の自慢みたいなものにはなっています。
一番覚えているのは、「学校のランチにマクドナルドを注文できた」ことです。
母親が学校に子どもを預けた後、近くのマックまで注文に行くと、お昼に注文したメニューを学校の食堂まで届けてくれるんです。「月に1回」と母親と約束をしており、毎月、その日が来ることを心待ちにしていたワクワク感は今でも忘れません。
ある時、母親に「今日は一番大きいサイズのコーラにして」とお願いをしたら、バケツサイズのコーラが食堂で待っていて、そこで初めてカルチャーショックを感じました。とても良い思い出です。
とまあ、こういった具合に、親がどれだけ悩んで、どれだけ重い決断をしたつもりでも、子どもの方は「マックを食べるのが楽しみだった」くらいしか覚えていないものです。
したがって、「適当に決めても良い」というわけではもちろんありませんが、あまり気を張りすぎるのも良くありません。ほどほどに悩んで、一度決断したら全力でサポートする、くらいに思っておけば良いと思います。
「現地校に通っていれば…」という後悔は否定できない
とはいえ、今になって思うのは「現地校に通っていれば今とは全く違う人生が待っていたはず」といった、ある種の後悔をふとした瞬間にしてしまうのもまた事実です。
筆者は英語圏ではありませんでしたが、英語にしろフランス語にしろ中国語にしろ、外国語をネイティブレベルで話せることは、人生単位で良い影響を与えてくれることに疑いはありません。
母親にも「どうせならインターナショナルスクールに入れてくれれば良かったのに」と冗談半分で話をすることがあります。
ですが、もし学校の雰囲気に適応できなかった時のリスクを考えると、自分が逆の立場だったとしたら、日本人学校を選んでしまうかもしれません。
日本人学校に通うメリットとデメリット
まずは日本人学校の元生徒の体験談を率直にお話ししましたが、続いて日本人学校に通うメリットとデメリットを経験者目線で解説していきます。
- 負担なく学校に通える
- 日本の文化や価値観に馴染める
- 日本人の「同じ立場の友達」と交流できる
- 現地の言語や文化に直接触れられない
- 日本の価値観から抜け出せない
- 学習が日本、現地のどっち付かずになる可能性がある
ご覧になるとわかりますが、いずれも納得感のあるものだと思います。
メリットの大部分は「日本に触れられる」ということです。日本人なので、日本の文化や価値観、そして日本人の友達に触れられて、悪いことはひとつもありません。
海外の文化や価値観に触れることも大切ではありますが、それは「日本の文化や価値観を理解した上で」という注釈が付きます。
まずは日本のことについてしっかりと落とし込んだ上で、それから海外に触れさせても遅くはありませんよね。
「海外の価値」をどれだけ重く見るのかがポイント
したがって、本質的に見れば「海外の価値」をどのように考えるのかで、メリットとデメリットの比重は変わってくるでしょう。
もし、「日本に戻ることが決まっている」ならば、日本により多く触れさせておかないと、「日本人なのに日本に馴染めない」というリバースカルチャーショックに陥る可能性があります。
現に、筆者の弟は現地の幼稚園に通っていたのですが、日本に帰国後、「国語の成績が他の科目に比べて明らかに悪い」「日本語を同年代の子に比べてうまく話せない」といった問題を、日本の公立学校側から指摘されていたそうです。
特別学級に入ることを打診されたくらい、当時は深刻だったようで、このようなリスクを背負うことになる、具体的には「日本語も外国語も中途半端で帰国する」ようなことになる可能性は考慮しておく必要がありそうです。
なお余談ですが、その後、弟はなんとか遅れを取り戻し、最終的には大学卒業を果たし、普通に働くことができています。
一方で、「日本に戻るかは未定」「世界を股にかけて活躍して欲しい」といったことであるなら、デメリットの方が気になってしまうでしょう。
「グローバル社会」なんて言葉は既に死語となりつつあるくらい、国という境界線が曖昧となり、今や「海外で生きていく」ことは普通のことです。
そんな時代をこれから生きていく子どもたちが、「学生時代に海外言語、文化に直接触れる機会がある」ことは、極めて大きなアドバンテージとなります。
もし、大学生や社会人になって海外に留学するとしたら、お金や時間、精神力など、あらゆるリソースを総動員しなければいけません。
これを考慮すると、学生時代に実質無料、は少し言い過ぎですが、「現地校に通わせる」という実生活の流れの中で海外に直接触れさせられるのは、とてつもない魅力だと言えるでしょう。
日本人学校で勉強を進める注意点を「元生徒の現役講師」が徹底解説
まずは「元生徒」目線で日本人学校の体験談を率直にお伝えしましたが、ここからは「現役講師」目線で、「日本人学校の勉強」というテーマを深掘りしていきます。
前提として、筆者はこれまで、オンライン家庭教師サービス「まなぶてらす」において、下記の2人の現地在住の生徒を指導してきました。
| 指導実績のある生徒 | |
|---|---|
| 生徒A | ・アメリカ東海岸在住 ・現地校に通学 ・日本語、英語ともにネイティブ ・帰国に備えて数学を指導 |
| 生徒B | ・シンガポール在住 ・日本人学校から現地校へ転校 ・日本語、英語ともにネイティブ ・帰国はしないが日本の勉強に触れたい |
いずれも現地在住で、英語をネイティブレベルで話すことができます。
生徒Aは帰国の見込みということで数学を指導していましたが、そのまま現地で生きていく流れとなったため、途中で指導を打ち切りとなりました。
生徒Bは海外で育ち、もともと日本語が話せなかったそうです。日本人学校へと通うことで日本語がネイティブレベルとなり、その後現地校へと転校するという流れでした。
現地の教育機関を上手に使い、日本と海外の2つの要素を上手に取り込んでいると感じました。
ともあれ、このような生徒を指導した経験をもとに、日本人学校で学習を進める注意点を解説していきます。
現地の言語は「ほとんど身に付かない」ことを覚悟しておく
最も大切なことが「現地の言語が身につくのか」ということです。
結論から言えば、筆者のパターン、つまり「日本で育って一時的に海外へ在住し、日本人学校で育って帰国する」ようなパターンでは、まず間違いなく「話せるようにはならない」でしょう。
筆者は中国語圏に在住していましたが、「ニーハオ(こんにちは)」「シェイシェイ(ありがとう)」「ハオツー(美味しい)」しかわかりません。「数年間現地に住んでいたにもかかわらず」です。
とはいえ、当時はまだ2000年台だったので、「グローバル化」の言葉が台頭してきたくらいの時代背景。今はさすがに、当時の環境よりも改善されているとは思いますが、「日本人」の枠から外に飛び出すことが難しいのは間違いありません。
対策:現地のコミュニティに触れる機会を作る
この問題の対策としては、「現地に触れる機会を作る」しかありません。
「日本人学校でも現地の言語の学習は行うから、対策の必要はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
確かに、これは事実です。しかし、よほど力を入れている学校でない限り、「日本の学校で行う外国語学習」と大差ないはずです。
そして、「日本の学校で行う外国語学習(英語の指導)」を受けてきた私たち大人は、英語を話せるようにはなりませんでした。つまり、日本人学校での外国語指導で現地の言語が話せるようにはならないことを意味します。
実際、シンガポール在住の「生徒B」に対して、「日本人学校ではどんな英語の勉強をしたの?」と聞いたら、「アルファベットの読み書きとかで、英語を話せる自分にとって何の役にも立たなかった」と話しています。
つまり、「日本の学校の英語指導と大差がない」ということです。当然、話せるレベルまでは至りませんよね。
したがって、「現地のコミュニティ」に触れる機会を能動的に作り、可能な限り「日本語NG」の環境に身を置けると良いでしょう。
帰国の可能性がある場合「リバースカルチャーショック」に注意する
もし帰国の可能性がある場合、「リバースカルチャーショック」に注意をしましょう。
日本人学校に通っていれば問題はないとは思いますが、家庭での食生活や習慣が「現地ナイズ」されてしまうと、どうしても日本の価値観からはみ出てしまいます。
もちろん、日本の価値観からはみ出すことは全くもって悪いことではないのですが、これが行き過ぎると帰国時に馴染めず、結果的に子どもが辛い思いをすることにつながってしまうはずです。
対策:家庭にて日本文化の浸透を促す
対策としては、「家庭にて日本文化の浸透を促す」しかありません。
食生活や生活習慣、言語や価値観など、日本の価値観に触れさせることで、「日本の価値観と現地の価値観は異なるものなんだな」ということを、肌身を持って実感させます。
幸い、筆者は海外といってもアジア圏でしたので、そこまで大きな価値観の違いはありませんでした。
しかし、欧米など文化圏までもが全く異なる環境に長期間いてしまうと、日本とのギャップが生じるのは無理もありません。
繰り返しにはなりますが、日本と異なる価値観に触れることは全く悪いことではないので、「海外の価値観と日本の価値観が異なる」ことを意識づけするために、家庭での教育に力を入れましょう。
現地で育った場合「国語力の遅れ」に注意する
こちらは要注意ですが、「国語力の遅れ」は気にしておくべき問題です。
「家庭でも日本語で、日本人学校に通わせている」ようなパターンでは、国語力に大きな影響はないと思います。筆者がこのパターンですが、国語は他の教科に比べて苦手ではあるものの、こういった形で文章を執筆できているくらいには日本語を扱うことができています。
一方で、先述のように「筆者の弟」のような「現地校に通っている」「現地校に通った後に日本人学校に転入する」ようなパターン、あるいは「自宅では現地の言語、日本人学校では日本語」といった形では、国語力の遅れに悩まされるかもしれません。
実際、筆者の弟は帰国後、「国語だけ明らかに成績が悪い」といった指摘を受けましたし、これまで指導してきた生徒A、生徒Bともに、会話は日本語ネイティブレベルでしたが、
- 漢字が読めない
- 詰まりながら音読をする
- 日本語で論理的に説明できない
このような問題が確認できていました。
対策:教育サービスを積極的に利用
対策としては、何らかの教育サービスの利用が求められるでしょう。
「日本語」ではなく「国語」なので、どうしても家庭での指導だけでは限界があります。
「日本語を使った論理的な会話」「常用漢字を使った読解」といった、教育面での専門性を求められる領域となるので、教育サービスの利用が好ましいです。
もちろん、日本人学校における学習で問題がなさそうなら、無理に教育サービスを利用しなくても良いでしょう。
しかし、日本人学校は日本の学校のような「受験を意識した学習」ではなく、あくまで「日本の学習」をするだけなので、学習の強度はどうしても落ちます。
したがって、子どもの習熟度を注意深く観察し、必要であれば教育サービスの利用を検討しましょう。
現地の教育サービスの利用は選択肢が少なくコスパが悪い
さて、ここにきて「教育サービス」について話が進みましたが、では実際に現地にて教育サービスを利用することは現実的なのでしょうか?
結論から言えば、現地でも教育サービスの利用は可能でしょう。ただし、「日本人在住者が多い地域に住んでいる」「教育資金に潤沢な予算がある」という注釈付きですが。
例として、過去に私たち「まなぶてらす」がお客さまに対してインタビューを行った「リアルインタビュー企画」にて、アメリカ在住のお客さまにインタビューした時のやりとりを引用します。
現地では絶対にありえない環境がオンラインを通して実現しています。日本語のプロの先生にこの内容、クオリティの授業をしてもらうことは現地では不可能です。
万が一、現地にこんな授業があったとしても、この値段の3倍どころじゃ効かないと思います。この質のものをこの価格で受けられるのはとてもありがたいです。毎日でも受けたいくらいです。
このお客さまは「日本語レッスン」をご利用いただいていて、「日本語のプロの先生にこの内容、クオリティの授業をしてもらうことは現地では不可能」といったお言葉をいただきました。
これに加えて「万が一、現地にこんな授業があったとしても、この値段の3倍どころじゃ効かないと思います。」ともお話しいただいております。
要するに、
- 現地には日本の教育サービスの選択肢が少ない
- あったとしてもかなり割高
- 上記理由から教育サービスの利用は困難
ということになります。
対策:オンライン家庭教師で日本在住講師に指導を仰ぐ

| サービス名 | まなぶてらす |
|---|---|
| 運営企業 | 株式会社ドリームエデュケーション |
| サービス開始 | 2016年5月 |
| 授業時間 | 50分 |
| 授業料 | 1,600円〜 |
したがって、対策としては「オンライン家庭教師」を利用することがあげられます。
オンライン家庭教師なら、日本の外に住んでいても「日本と全く同一の条件で授業を受けられる」ので、料金や講師のクオリティなどに縛られず、自由に利用することができます。
特に私たち「まなぶてらす」は、海外在住の方に向けて下記のような特徴を打ち出しています。
- パソコンやタブレットがあれば今日から始められる
- 月謝制ではなく都度予約制なのでその都度お支払い
- 入会金も施設管理費も一切なし。授業料以外にお金はかからない
- 予約、キャンセルは3時間前まで可能
- 24時間体制なので時差を気にする必要がない
- 採用率3割程度の質の高い自慢の先生たち
- ミスマッチを防ぐ先生検索機能を用意
- ZOOMを使ったオンライン自習室を完備
- お試しできる「初回無料体験レッスン」を多くの先生が実施
この中でも特に注目すべきなのが「都度予約制」「24時間体制」である点です。
海外在住の場合、どうしても現地のスケジュールで動かざるを得ず、指定した時間帯に授業ができなかったり、そもそも利用できる時間帯に授業が受けられないこともあったのが、従来型のオンライン家庭教師でした。
しかし、「まなぶてらす」では「都度予約制」「24時間体制」とすることで、この問題を克服しています。もちろん、24時間、どの時間でも料金は変わらず、一律で通常料金での提供です。
初回無料体験レッスンで
\オンライン家庭教師をスタート/
今なら2,000円相当のポイントもプレゼント!
まとめ
日本人学校、現地の学校、どちらに通うのかは悩みの種ですが、正解はなく、合う合わないなど、子どもの人生にとってどちらがベターなのかという視点を持つことが大切です。
記事で紹介した経験者による本音を参考にしてみてください。
少なくとも筆者は、日本人学校に通った経験をネガティブには捉えておらず、とても良い経験だったと前向きに捉えられていますよ。